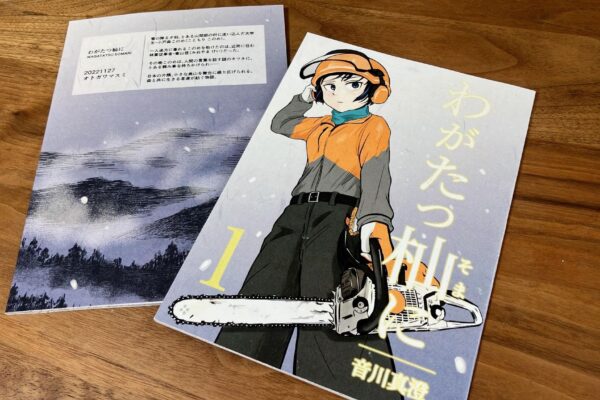2000年以降、毎年のように極地を旅してきた荻田さん。2012年に、新たな旅である「100マイルアドベンチャー」を始めます。小学6年生を対象に国内を100マイル、キャンプしながら歩く旅です。
青木:100マイルに参加する子はどんな感じなんですか?
荻田:参加者に多いパターンは、親が知っていて、子どもに「どう?」と声かけて、やる気になったら、親がエントリーして、子供には事後報告。「申し込んどいたから」「え、俺それ行くの」(笑)
青木:しかも10日以上。
荻田:だから初めは全然乗り気じゃない子もいるし、言われたから来ました、もう絶対行きたくないという子もたまにいますよ。もう、ほんとに、どよんとした感じで、初日のスタート地点に立ってるような。
でも、途中から楽しくなってくるし、 最終日には、泣きながら解散みたいなね。
で、参加させてくれてありがとうってお父さんに言いながら帰るんです。乗り気じゃなかったけど、やってみたら良かったって。そういうの、でかいじゃないですか。
青木:確かに…
荻田:そこで、例えば子供の主体性を育みましょう、子供の自発性を優先しましょう、参加したくないんだったら、参加しなくていいよとなった場合、その子の主体性を大事に、自発性を優先してるということですが、 それが正解なのか不正解なのか、結構難しいというか、危ういですよね。
それで、本来楽しめた場に参加できないかもしれないし。
青木:そうです。
荻田:だからと言って強制的になんでもかんでも無理やり突っ込めばいいという話でもなくて。
それはやはり信頼関係。親と子の信頼関係だし、親御さんが我々を信頼してくれて送り出してくれるっていう信頼関係もあるし、我々と子供たちとの信頼関係もあって、その全部の信頼関係がうまくいった時に いい方に成立するので、どれかが崩れちゃうと、 この無理やり参加させられた子供にとっては、もう、やっぱ行かなきゃよかったよっていうイベントで終わっちゃう。でも、そうしちゃいけないので、全部の信頼関係をうまくいかなければいけない。となった時に、また我々と子供の信頼関係を築くには、やっぱりある程度時間も必要になりますよね。
だからこそ、2桁日数は欲しいなと。
青木:なるほど…。最初の年は?
荻田:初回は参加が3人でした。3人で13日間歩きましたが、めちゃくちゃ濃かった。
青木:濃密ですね(笑)
荻田:めちゃめちゃ濃い。 スタッフも3人。
青木:家族みたいな感じですね。
荻田:全員、他人なんですけど、1個のでっかいテントで毎日。ほんと、家族ですよね、ほぼ2週間ずっと一緒なのですごい濃くて、これは面白いなと思いました。もう、毎年やろうと思って、翌年からずっと続けてます。
青木:毎年続けてると何か見えてきますか?
荻田:6年目の2017年から過去参加した子をスタッフに入れてるんですよ。小学6年生の時に参加してきた子が、高校生になって、スタッフ側をやると。さっきの視座の話と同じで、参加者の立場で見るのと、スタッフの立場で臨むのは、全然変わるわけですよ。
青木:そうでしょうね…
荻田:大きいテントやキャンプ道具を運ぶ同行車両があるんですよ。買い出しに行ったり、先回りしてキャンプの準備をしたりとか、スタッフは子どもたちが歩いてる間に見えない動きをやってるわけですよ。
でも、子供たちからすると、車は楽でいいなっていうわけです。 うわ、俺たち暑い中、荷物担いで歩いてんのに、車いいなって(笑)
青木:はい。
荻田:そこで言うわけですよ。「お前らがスタッフやってごらん」て。どれだけ大変かわかるからと。それこそ雨でも降ったら、テントもタープもびしょ濡れで、重たくなったやつを撤収したり、また次のキャンプ場でタープ立てるとか、それもどしゃぶりでもやんなきゃいけない。でも、子供たちからすると、キャンプ場ついたら、もうあるから知らないわけですよ。あの5メーターぐらいのでかいスクエアタープをどしゃぶりの中立てるのがどんだけ大変かっていうのを 分かんないわけですよ。
でも、高校生になってスタッフやった時に、あ、そうか、こんな大変だったんだっていう裏側を初めて知るんですよ。
6年生で参加してる時は、それはそれで、1つの旅としてはいいんですけども、高校生でスタッフをやった時に初めて自分が見えなかったところまで見えてくるので、 そこで完成というかね。
青木:なるほど…
荻田:そういう意味で言うと、自分は主催者ですが、子どもたちの立場になったことないから、実は永遠に知らない、完成しない。
でも、彼らは参加したことあるし、スタッフ側もやってるから、ある意味で俺より見えてるのかもしれない。
青木:今後も続けますか?
荻田:毎年続けていくし、今後どうしていくかは分からないですけど、できれば何か文献みたいのを作りたいですね。
青木:自分がいなくてもできるように。
荻田:自分がいなくなってもできなきゃいけないし、多少変化はもちろんしてくると思いますが、その根本のメンタリティーは崩さずに 続けていく。それがね、日本全国で同時多発的にできればもっといいだろうし。なんか、そういうものにできればいいなと思うんです。
青木:若者を北極に連れて行くというのもやられてましたが、その延長線上にあるんですか?
荻田:初めは同じだと思わなかったですが、やってみたら同じですね。
北極に参加した若い奴らが、その年の100マイルに2人ぐらい、遊びに来たんです。
こいつら、一緒に北極行ったんだよと子どもたちに話したんですが、2、3日一緒にいたら、その北極行った若い子たちが、 荻田さん、なんか 見たことある感じがするんですけど、この感じ、北極行ったのと同じだと。
青木:そうなんですね。
荻田:夏の日本と冬の北極なので全然違うんですが、 やってることは基本的に変わらない。
青木:難易度は違うかもしれないですね。コントロールというか、管理の。
荻田:でも、基本的には同じ。変わんなかったですね。
青木:目的は違うんですか?
荻田:目的もあんまり変わんないですよ。
青木:そうなんですね。
荻田:基本的には同じです。自分の知ってる世界の外側にね、出てみるという。 知ってる世界の外を見て、で、また元の世界に帰ってくるっていう。それは同じ。旅に出るということ。
青木:旅…
荻田:旅に出るって、そういうことじゃないですか。自分の知ってる世界から外に出て、で、帰ってきたら、もう知ってる世界じゃないんですよ。
青木:はい、はい、違う。そうですね。
荻田:経験をして、違う目を持った人間がまた元の世界に帰ったら、もう元の世界はもう元の世界じゃないわけですよね。その積み重ねが大事であって。
青木:自分は自分の判断で動いていると思ってるんで、ある意味成功体験をしてるわけですね。
荻田:本人はそうです。そうです。
青木:そうすると、元の日常に戻ってきた時に、必ず目線は変わってる可能性がありますよね。
荻田:全部繋がってきますからね、そこにね。そういう経験をしてほしいなと思ってます。
青木:参加者がその後、どう変化したか、いろいろ見て知ってらっしゃるんですか?
荻田:結構今でも繋がってる子も多くてですね。初回の子がやっと大学卒業した年なので、これからだと思うんですけど、面白い子、多いですよ。ここにもよく東京、神奈川の子が遊びに来ることがありますし。ま、まだ、これからかな。
青木:楽しみですね。
荻田:その子たちがどうなるかはもう、20年、30年経たないとわかんない。それは北極の方もそうかな。その後、また北極行ったやつもいるし…。何かしらやってる子も多いですよね。
青木:そこは何かを期待してるわけではない?
荻田:全然何も期待してないです。期待はしてないけど、まあ、何かやってりゃ何か起きるだろうなっていう確信はあります。
(インタビュー収録:2023年5月)
5回目へ続きます。
冒険研究所書店はこちら。
100milesAdventureについてはこちら。
TEXT:木田 正人 Photo 金久保誠